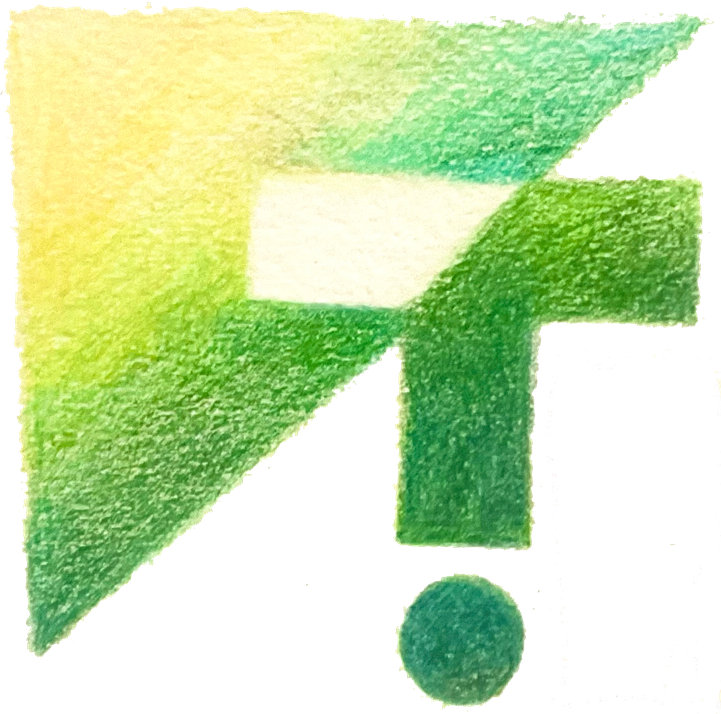心療内科 強迫性障害 発達障害 統合失調症 うつ病について
心療内科
心療内科とは
心療内科は、ストレスや心理的な要因によって身体に症状が現れる心身症などを主な対象とし、身体的な病気と精神的な問題を総合的に扱う診療科です。この分野では、身体の病気が精神的な要因やストレスによって悪化することを理解し、治療します。
どんな症状があるのか
心療内科でみられる症状は、胃痛、下痢や便秘などによる腹痛、吐き気・嘔吐などの消化器系の症状、喘息のような症状や過呼吸などの呼吸器症状、血圧上昇、動悸、胸痛などの循環器症状、頭痛、めまい、不眠などの神経系の症状、他には強い倦怠感や疲労感、蕁麻疹などの皮疹、自律神経失調症、摂食障害なども含まれます。
心療内科の治療の流れ
心療内科では、ストレスや心理的な要因によって身体症状が出現することを想定しているため、まずはしっかりとした問診を行い、必要に応じて身体症状の原因となる病気が存在しないか血液検査、画像検査(レントゲン検査、CT検査、MRI検査)などを行うことが重要となります。また、一般的にストレスの感じ方などは個人差が大きく、ストレスの度合いを定量的に測ったり、性格の傾向を把握するための心理検査を行う場合もあります。
治療法としては、出現している身体症状に対して必要に応じて対症療法(それぞれの症状にに対しての治療)としての薬物療法、精神療法や心理療法(認知行動療法、カウンセリング)
を通して、ストレス対処法や問題解決能力の向上を目指すこと、生活指導などを主体に行っていきます。また、摂食障害などで生命活動に危険が及ぶ場合には入院治療を行うこともあります。
強迫性障害
強迫性障害とは
強迫性障害は、強迫観念と強迫行為を特徴とする精神疾患であり、これらの症状により日常生活に大きな苦痛や支障をもたらします。
強迫性障害の原因
強迫性障害の正確な原因はまだ解明されていませんが、遺伝的要因、脳機能のバランスの異常、環境要因などが複雑に絡み合っていると考えられています。
強迫性障害の症状はどんなものか
強迫観念とは、頭から離れない、不快で反復的な思考、イメージ、または衝動のことです。これらの思考は、非合理的で望ましくないものであると分かっていても、コントロールすることができません。よく見られる強迫観念として、不潔恐怖(細菌、ウイルス、汚れなど)、加害恐怖(自分自身や他人危害を加えることへの恐怖)、確認恐怖(自分の行った行動が適切に行われているかどうかに対する恐怖)、不道徳恐怖(道徳や宗教に関する過剰な不安)などが知られています。
強迫行為とは、強迫観念によって引き起こされる不安を軽減するために行う反復的な行動や精神的な行為のことです。これらの行為は、一時的に不安を軽減するかもしれませんが、根本的な解決にはならず、強迫行為自体に苦痛を伴うことがほとんどです。具体例としては、不潔恐怖に対しての過剰な手洗いや消毒、確認恐怖に対しては、頻回な行為の確認(何度も鍵やガスの元栓の確認を行うなど)などがあります。
強迫性障害の治療法
強迫性障害の代表的な治療法は、薬物療法、認知行動療法(暴露反応妨害法)で、これらを組み合わせて行っていきます。また、稀に上記の治療法で効果が見られない場合には、電気けいれん療法(ECT)が検討されることがあります。
発達障害
発達障害とは
発達障害は、生まれつきの脳の発達に関連する神経発達の障害によるものの総称で、個人の思考、感情、行動、学習に通常よりも偏りを持つ特徴がみられます。この偏りの程度は、個人によって様々であり、外見からは分かりにくいため、周囲に理解されにくいことも多いです。発達障害でも代表的なものは、自閉スペクトラム症(以下、ASD)、注意欠如多動症(以下、ADHD)、限局性学習症(以下、LD)です。発達障害は早期に診断され、適切な支援や治療を受けることで、個人の能力を最大限に活かすことが可能となります。
発達障害の原因
発達障害の正確な原因はまだ解明されていませんが、遺伝的要因、脳の発達の偏り、環境要因などが関連していると考えられています。
発達障害の症状はどんなものか
発達障害の症状は、どのタイプの障害かによって、症状が異なります。ASDでは、社会的な相互作用やコミュニケーションにおける困難さ、反復的で常同的な行動や興味の範囲の限局が特徴的な症状です。ADHDでは、不注意による頻回なミス、集中力の持続の難しさ、衝動的な行動、落ち着きのなさなどが特徴的な症状です。LDでは、読む、書く、計算するなどの特定の学習領域において通常の知的能力を持っていても困難が生じるということが特徴的な症状です。
発達障害の治療法
薬物療法については、ADHDには有効な薬物が存在しています。一方ASDにおいては、対症療法的な使用にとどまっています。
それ以外では、行動療法(社会的なスキルを教えたり、望ましい行動を強化したりするための技法)、認知行動療法(感情や行動を改善するために、考え方や反応を変えること)、環境調整(自身の特性にあった環境を選択する、周囲と協力しそのような環境を作っていく)、心理教育(学習プログラムや書籍などでの自己学習によって障害特性を理解する)などが知られています。
統合失調症
統合失調症とは
統合失調症は、思考、感情、行動において大きな障害が生じる精神疾患です。これらにより社会的機能や日常生活にさまざまな影響を及ぼします。統合失調症は、早期に診断し、適切な治療を受けることが重要ですが、症状の程度は個々で異なり、診断や治療には時間がかかることもあります。
統合失調症の原因
統合失調症の正確な原因はまだ解明されていませんが、遺伝的要因、環境的要因(ストレスや違法薬物の使用など)、生物学的要因(脳内の神経伝達物質の異常)が複雑に絡み合って発症すると考えられています。ドパミンなどの神経伝達物質の機能障害が想定されています。
統合失調症の症状はどんなものか
統合失調症の症状は大きく分けて、陽性症状(本来あるはずのないものが現れる)、陰性症状(本来あるはずものが低下する、なくなる)、認知機能障害(物事の認識が難しくなる)が挙げられます。陽性症状の代表的な症状として、幻覚(視えるはずのないものが視える幻視、誰もいないもしくは周囲はそんなこと言っていることとは異なる声が聞こえてくる幻聴など)、妄想(現実にはありえない考えが浮かんできて、確信するなど)、思考の混乱(発言にまとまりがなく、辻褄の合わない言動をするなど)が挙げられます。陰性症状は、感情の平板化(喜怒哀楽などの感情が乏しくなる)、意欲の低下、興味や関心の低下、自閉(引きこもり)などがあります。認知機能障害については、集中力が続かない、記憶力が低下する、思考や判断力が低下するなどを認めます。
特に陽性症状は、嫌ものが視えたり、自分に対して否定的な幻聴、周囲から非難されていると感じてしまう被害妄想など自分にとって不快なことが多く辛い症状であり、それによって自傷や他害に繋がるケースもあります。
統合失調症の治療法
統合失調症の治療法は、薬物療法とリハビリテーションが主であり、これらを組み合わせて行っていきます。前述したような陽性症状が活発であり、日常生活で大きな問題が生じている場合は、入院治療を行うこともあります。また、稀に上記の治療法で効果が見られない場合には、電気けいれん療法(ECT)が検討されることがあります。
鬱(うつ)
鬱(うつ)とは
鬱(うつ)は、正確には「抑うつ気分」といい、気分の障害に分類されます。症状として、きっかけもないのに妙に気分が沈む、憂うつで、悲しく、淋しく、しおれがちになるなどの状態がみられます。健康な人でも一過性にうつ(抑うつ気分)を自覚することはありますが、それが一定期間持続することは稀であり、通常は自然に正常な気分に戻ります。このような抑うつ気分が持続し他の症状を伴う状態が「抑うつ状態(うつ状態)」であり、うつ状態が長期に及ぶものが「うつ病」です。
鬱(うつ)の原因
この抑うつ状態は、様々な原因から生じます。代表的な疾患として、うつ病、適応障害、躁うつ病(双極性障害)などが挙げられます。これらは、併存やもしくは移行することがあることも知られています。
ここからは、抑うつ状態を呈する代表疾患であるうつ病について説明していきます。最近の疫学調査では、人生で1度でもうつ病になってしまう人の割合は、6%であり、およそ20人に1人が人生で1度はうつ病の診断基準を満たすような状態を経験すると言われています。海外のデータでは、うつ病の生涯有病率は10~20%以上というデータもあります。
うつ病は女性が男性よりも2倍ほど発症しやすく、周産期に伴うホルモンバランスの変化によって引き起こされる場合があるのも一因と考えられています。また、うつ病は他の疾患と併存することが多く、精神疾患ではパニック障害、強迫性障害、PTSDなどの不安障害、パーソナリティ障害、アルコール依存症などが代表的なものです。身体疾患との関連も明らかになっており、身体疾患をもっている患者はうつ病の有病率が高く、うつ病と身体疾患がそれぞれを増悪させる因子であり、精神学的介入が身体疾患の予後を改善させるとが知られています。うつ病の発症には様々な要因が関与していると考えられ、遺伝的要素や心理社会的要素が知られています。
うつの症状はどんなものか
- 抑うつ気分
- 疲労感や気力の減退
- 睡眠の変化:不眠、過眠
- 食欲の変化・体重の変化
- 興味・関心や喜びの喪失
- 精神運動性の焦燥もしくは抑制
- 無価値観あるいは自責感
- 思考力や集中力の減退
- 自殺念慮
これらの症状が少なくとも5個以上、同じ2週間の間に存在する場合は、うつ病がの可能性を考える必要があります。
うつ病の治療法
うつ病の治療法は、様々ありますが、薬物療法や認知行動療法などの精神療法が代表的な治療法です。他には修正型電気けいれん療法、経頭蓋磁気刺激法などが知られており、これらは特殊な技法や装置を用いるため、限られた医療機関で行うことになります。
社交不安障害
社交不安障害とは
社交不安障害(社会不安障害)とは、他者との交流や社会的な場面で極度の不安や緊張を感じる疾患です。従来、対人恐怖症と呼ばれた状態にほぼ相当しています。これは、単なる恥ずかしさや緊張感を超えて、日常生活において苦痛を伴い、大きな支障をきたす場合があります。主に会話をすることや集団の中で目立つことを避けようとする行動に現れます。会食に対する強い恐怖を抱くケースもみられます。
社交不安障害の原因
社交不安障害の正確な原因はまだ解明されていませんが、遺伝的要因、脳機能のバランスの異常、環境要因、社会的な要因などが複雑に絡み合っていると考えられています。
社交不安障害の症状はどんなものか
社交不安障害では、対人場面における、強い不安や緊張、自律神経症状に伴う身体症状、回避などがみられます。社交不安障害では、人前で話す、食事をする(会食恐怖などとも呼ばれる)、字を書くなどの周囲の注目を浴びるようなシチュエーションに対する強い不安や緊張を認めます。そのようなシチュエーションにおいて自律神経の交感神経優位となり、赤面、発汗、震え(声や体)、動悸、吐き気、息苦しさが出現します。息苦しさは、パニック発作に至る場合もありますが、頻度としては多くはありません。また、強い不安や緊張、それに伴う症状は苦痛を伴うため、それらを感じるようなシチュエーションを日常生活で避けるようになります。これを回避と呼びます。
社交不安障害の治療法
社交不安障害の代表的な治療法は、薬物療法、認知行動療法(暴露反応妨害法など)、ライフスタイルの改善で、これらを組み合わせて行っていきます。薬物療法では、抗うつ薬や抗不安薬を用いて行うことが一般的です。認知行動療法では、特定のシチュエーションにおける自分の不安や恐怖に対する誤った思考を認識し、実際の状況に基づいて考え直すことを学びます。暴露療法は、不安感や緊張がある程度コントロールできている状態において、段階的に苦手と感じているシチュエーションに対して慣らしていくという治療法です。社交不安障害では、自律神経の中でも特に交感神経が過度に優位になった状態となっており、それを是正できるようなライフスタイルの確立も大事なっています。具体的には、十分な睡眠時間を確保すること、規則正しい生活を送ること、適度な運動習慣、交感神経優位になるようなシチュエーション(過度なストレス、プレッシャー、カフェインの摂取)を可能な範囲で避けること、リラクゼーション(瞑想や、深呼吸)などが有用と言われております。
パニック障害
パニック障害とは
パニック障害は、突然の強い恐怖感や不安感が繰り返し襲う疾患であり、通常は急速に発生します。パニック発作(不安発作)は、自律神経症状による身体的な症状と精神的な症状が出現し、非常に強い苦痛を伴います。死の恐怖を感じることもみられます。一般的に男性より女性の方が発症しやすく、中年以降よりも若年で発症しやすいと言われています。
パニック障害の原因
パニック障害の正確な原因はまだ解明されていませんが、遺伝的要因、脳の機能、環境要因、心理的な要因などが複雑に絡み合っていると考えられています。一度パニック発作を起こすと、類似した状況で発作が出現しやすくなります。
パニック障害の症状はどんなものか
パニック障害の症状は、パニック発作(不安発作)、予期不安、広場恐怖に分けられます。パニック発作とは、突然の強い動悸や強い心臓の鼓動、胸部の圧迫感、胃苦しさや窒息感、冷汗、めまいやふらつき、嘔気、気が遠くなるなどの症状が出現し、それにより「自分が制御できなくなる」という死の恐怖感が出現している状態です。通常は強い苦痛を伴い、強固に記憶されることが多いです。
予期不安とは、日常生活において、またパニック発作が起きるのではないかという不安が付き纏っている状態を指します。広場恐怖とは、パニック発作が起きた際にすぐに逃げられないようなシチュエーション(電車、バス、エレベーターなどの閉鎖空間)に対して強い恐怖を感じそれを避けるようになることを指します。
パニック障害の治療法
パニック障害の代表的な治療法は、薬物療法、認知行動療法(暴露反応妨害法など)、ライフスタイルの改善で、これらを組み合わせて行っていきます。薬物療法では、抗うつ薬や抗不安薬を用いて行うことが一般的です。
認知行動療法では、パニック発作によって形成された自分の不安や恐怖に対する誤った思考を認識し、実際の状況に基づいて考え直すことを学びます。暴露療法は、パニック発作がある程度コントロールできている状態において、予期不安や広場恐怖を軽減させるために段階的に苦手と感じているシチュエーションに対して慣らしていくという治療法です。
社交不安障害と同様に、パニック障害では、自律神経の中でも特に交感神経が過度に優位になった状態となっており、それを是正できるようなライフスタイルの確立も大事なっています。具体的には、十分な睡眠時間を確保すること、規則正しい生活を送ること、適度な運動習慣、交感神経優位になるようなシチュエーション(過度なストレス、プレッシャー、カフェインの摂取)を可能な範囲で避けること、リラクゼーション(瞑想や、深呼吸)などが有用と言われております。
双極性障害害
双極性障害とは
双極性障害(躁うつ病)は、気分が高揚する「躁状態」と、反対に落ち込む「抑うつ状態」が周期的に現れる精神的な疾患です。この疾患は、感情の浮き沈みが激しく、躁状態の程度によってⅠ型とⅡ型に分けられ、感情の浮き沈みが激しく、しばしば日常生活に深刻な影響を与えることがあります。そのため、治療が遅れると仕事や人間関係、さらには身体的な健康にも影響を及ぼすことがあります。
双極性障害の原因
双極性障害の正確な原因はまだ解明されていませんが、遺伝的要因、環境的要因(ストレスや違法薬物の使用など)、生物学的要因(脳内の神経伝達物質の異常)が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
双極性障害の症状はどんなものか
双極性障害の症状は、躁状態(躁病相)と抑うつ状態(うつ病相)のどちらのう状態かによって大きく異なります。躁状態とは、気分が爽快(爽快気分)で、高揚(気分高揚)し、場合によっては何でもできてしまうような感覚(万能感)を認めます。また、エネルギーに満ち溢れ、普段より短時間の睡眠でも疲れない(睡眠欲求の減少)、普段は行わないような活動をする(過活動)、衝動的で短絡的に行動してしまう(衝動行為)、いろんな考えがどんどん浮かんできて集中できなくなる(観念奔逸)などの症状を認めます。重症例では、幻覚(幻聴や幻視)、妄想(特に誇大妄想)などが出現し、自制がきかない状態となり、社会的に大きな問題に至る場合があります。
重症の躁状態を認めるものを双極Ⅰ型障害、軽度の躁状態にとどまるものを双極Ⅱ障害型を読んでいます。抑うつ状態では、うつ病と同様に、抑うつ気分、意欲低下、気力の減退、不眠、食欲低下、興味・関心や喜びの喪失、精神運動性の焦燥もしくは抑制、思考力や集中力の減退などを認めます。また、まれに躁状態と抑うつ状態が同時に出現する躁うつ混合状態という状態に至る場合もあります。
双極性障害の治療法
双極性障害の治療法は、薬物療法と精神療法が主なものであり、規則正しい生活習慣、適切な睡眠、ストレス管理が症状の改善に役立ちます。また、アルコールや他の薬物の使用を避けることが重要です。前述した双極Ⅰ型障害と呼ばれる躁状態で日常生活で大きな問題が生じ、入院治療を行うことも少なくありません。また、上記の治療法で効果が見られない場合には、修正型電気けいれん療法(ECT)が施行されることがあります。
監修 宮保嘉津真